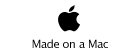My Blog

展示評「北国の染織」
5月15日に、東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館で行われている特別展「北国の染織」を見に行った。
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/j/index.html
東北の各地方で特徴的な染織を地域ごとに展示し、その最後にはアイヌ民族展示も含ませる、民芸的視点からの展示構成だった。東北地方では19世紀までは麻が中心で木綿は十分浸透していなかったという歴史的背景ともに、そのなかで花開いた地域の文化、津軽のこぎん、岩手の「夜着」、そして庄内の「被衣」などの特徴が大変わかりやすい形で展示してある。そして民芸の同人達がそこに読み取った日常の美がどのようなものか、わかってくる。東北日本の伝統的衣類文化という点、衣類文化を18-20世紀初頭という形で、つまり近世的な伝統と理解することの面白さ、なぜそれらの染め織文化が失われたのかという点など、さまざまな形での思考が可能である。また人々がそれらの染め織の模様のモチーフをどのように選び取ったのかという点でも大変興味深い。
圧倒的な迫力があったのが、展示チラシにも大きく映し出されている岩手県の鉄線唐草文夜着である。大人の背丈を貼るかにこえるような寸法で、あたかも着る毛布のようなものだが、その染め織が大変美しい。表面の唐草文の落ち着いた色合いの良さはいうまでもないが、藍の裏地に白の刺し子模様も気持ちを落ち着かせる。別の夜着では、夢に鳳凰がでてくると縁起がいいということで、鳳凰が豪華に染められている。寝具文化の豊饒性がこれらの染め織には溢れんばかりである。なぜ今それがすたれてしまったのかと思ってしまった。このような夜着が出てくる背景には、木綿の普及がある。新しい材料をえることで新しい創造と快適さをもとめる形がつくられたのであろうか。個人的には祖母が私に二度程つくってくれた「綿入れ半纏」を想起した。綿に対する思い入れが、祖母達ぐらいまでの世代にはあったのだろう。
庄内の「被衣」は、北前船がもたらした江戸や京の風俗である。おもしろいのは女性が夜外出するときにはこれを被ってでたということだ。しゃれっけのある模様がついている。これを被ってでていく女性はどのような思いを頂いてたのか、などと想像心がくすぐられる。
材料について面白かったのは、紙布織仕事着というのもあったことだ。これは和紙から紙縒糸をつくり、それで折った布=紙布で制作したものである。さらに秋田の「祝いけら」はいわゆる蓑であるが、その材料は海藻である。なるほどそれならば耐水性もあるわけだ。これらをみていると、趣旨説明にある「雪深く厳寒な北国では、自生する樹木や植物に材料をもとめ、時間をかけて衣料の製作に取り組みました」という意味がしみじみとわかってくる。
そのなかで圧倒的な美しさを示しているのが、こぎん刺しである。特に東こぎんと呼ばれる織の特徴は大変魅力的である。藍と白の対称性が美しい。おもしろかったのは、東こぎんでは、木綿の稀少性ゆえに、何度も染め上げられて最後には黒くなるほどだったということである。これはアバコギンとよばれ年配の人が着るものだった。まさにこれは衣類のバイオグラフィ(個体史)である。その過程が地域文化のなかに埋め込まれているのだ。このような美しい文化も、20世紀つまり明治初期にはすたれていく。なぜなら木綿が定着してくるからだ。とはいえ、短期的にはそのことによってより木綿を利用したツヅレ刺し短着へが生まれた。それらもまた大変美しい。
このようにしてみてくるとある文化を一定の時代のなかで捉える事はより重要だと思う。人類学のなかでは常に現代性こそ最も知るべき事ととしてやかましく語られているが、この展示をみていてそうなのだろうかと思ってしまった。18-20世紀初頭という枠で、東北日本の衣料における染め織がいかなるものだったのか、その本質をとらえる作業は必要であり、そこに読み取るべき文化=人々の生活をつむぐ力はみなぎっている。そのこと自体明らかにされなければならない課題なのではないかと感じた。
またこの展示からわかるのは、このような体験は博物館でしかできないということである。時間も場所もばらばらな標本資料が組み合わされて展示が構成される。それゆえにみえてくる世界があるのだ。これらの衣類が日常生活にあっても、その民芸的美は輝くであろう。しかし標本化し、かつてそれが生きられた形=その社会文化的文脈があるかぎり、今回の展示で提供するような近世から明治末期という時間的幅と、東北日本という空間的広がりを一塊にして展望することはできない。博物館が提示する場の特性は、この点で現実には存在していない時間と空間を混ぜ合わせて作り出す事だと思う。
2012年5月18日金曜日