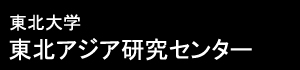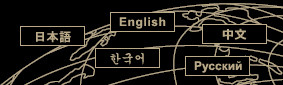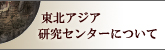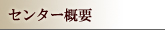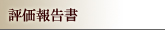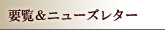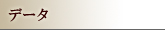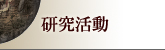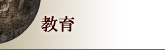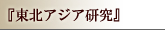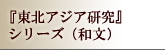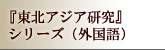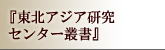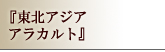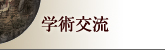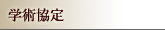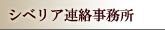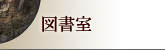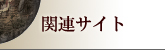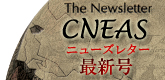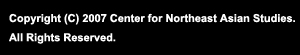東北アジア地域における模倣の土器文化
過去から現在まで“模倣”は単なる技術の継承を超えて社会のあり様に深く関わっている。模倣それ自体が地域や個人の親縁関係を表すとともに、権威集団の制度やモノの模倣はその権威を借りるために行われる。技術や素材獲得に必要な環境の違いのため、オリジナルの再現は一般には不可能だが、模倣の不完全ささえ社会を理解するための重要な情報源となりうる。また、モデルとの類似度は素材環境や技術的背景、あるいは「憧れ」「ライバル意識」など様々な要素が影響しており、当該社会の社会・政治的関係の理解に新たな軸を加えうる。
東北アジアでこうした模倣の最も顕著な例の一つが、中国製品の他国による模倣である。韓半島では三国時代に在地の土器が椀形化することが知られており、これは中国製の銅碗の模倣とされる(山本2017)。また、日本では律令制下で成立した土器のセットが、9世紀ころから中国産陶磁器を模倣し始める(西1982)。これらは、技術や素材が不足する中で、異なる材質を用いて再現を試みたものである。
これまで、中国製品の模倣の研究は形態や技術に焦点を当ててきた。しかし、異なる素材を用いる中で、認知される重要な差異の一つは色であろう。中国の銅碗はもともと黄金色、陶磁器は特徴的な白色や緑色をしている。こうした、色覚的な要素の模倣品への反映の程度は、これまで十分に検討されてこなかった。
以上の状況を踏まえ、本研究は中国の影響を受けた土器の変容の様相を、色調という認知的な側面と形態から検討する。対象は、中国の影響で器形が「椀」になったとされる平安時代の日本と三国時代の韓国とする。これにより、中国の影響下における文化変容のあり方を比較文化的に考察し、中国文化への憧れや影響の強さを明らかにする。本研究では対象物の色調を「土色計」と呼ばれる機械によって計測し、定量的なデータを得る。
一方で、過去の人間の認知に注目する「認知考古学」の一環として、松本1996や鐘ヶ江2003において縄文・弥生土器の色調分析が行われており、土器製作者が意図的に色調をコントロールした可能性が示されている。しかし、土器は土地固有の粘土から作ることから、その色調は地質環境に左右されうるため(鐘ヶ江2003)、色調に製作者の意図が反映されているかは土器の鉱物組成を踏まえる必要がある。そこで本研究は、考古学的手法と地質調査を組み合わせ、当該社会が表現可能な色の幅を、重要な参照枠組みとして検討する。これにより、広義の「石」文化と人間の関わりを、模倣品の色調の形成プロセスから考察する。
2019年度~2019年度
| 氏名 | 所属 |
| 辻森 樹 | 東北アジア研究センター |
| 阿子島 香 | 東北大学文学研究科 |
| 洪 惠媛 | 東北大学文学研究科 |
| 田村 光平 | 東北大学学際科学フロンティア |
| 舘内 魁生 | 東北大学文学研究科 |
| 早川 文弥 | 東北大学文学研究科 |