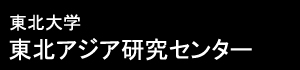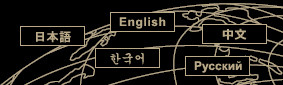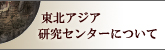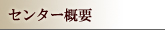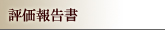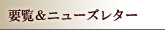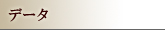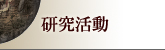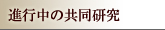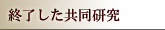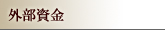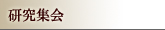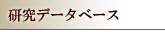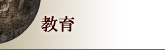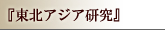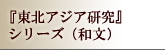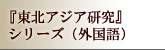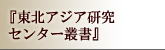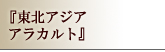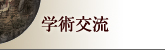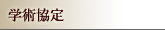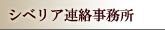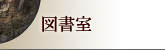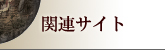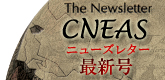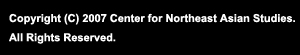|
瀬川 昌久 〔せがわ・まさひさ〕 東北大学 東北アジア研究センター 中国研究分野・教授 (兼)東北大学大学院 環境科学研究科東北アジア地域社会論講座 【専攻】 文化人類学 華南地域研究 【学位】 学術博士(1989年5月、東京大学) |
【略歴】
| 1957年9月 | 岩手県花巻市に生まれる |
| 1976年3月 | 岩手県立盛岡第一高等学校卒業 |
| 1981年3月 | 東京大学 教養学部教養学科卒業 |
| 1986年6月 | 東京大学 大学院社会学研究科博士課程退学 |
| 1986年7月 | 国立民族学博物館 助手 |
| 1989年4月 | 東北大学 助教授 教養部 |
| 1993年4月 | 東北大学 助教授 文学部 |
| 1996年5月 | 東北大学 教授 東北アジア研究センター |
| 2007年4月~2009年3月 東北アジア研究センター長 | |
【業績】
⇒ 東北大学研究者データベース
⇒ researchmap
【教育活動】
全学教育
文化人類学
大学院講義
地域環境・社会システム学セミナー
地域環境・社会システム学博士研修
東北アジア社会人類学
東北アジア民族誌
東北アジア歴史人類学
他大学講師
岩手大学(文化人類学)
東北文化学園大学(文化人類学)
【学外での活動】
第24回渋沢賞受賞(財団法人民族学振興会、1995年10月)
日本文化人類学会理事・評議員
【連絡先】
〒980-8576 仙台市青葉区川内 東北大学東北アジア研究センター
TEL : (022)795-7695
FAX : (022)795-7695
【研究紹介】
現代中国における親族組織・宗族(そうぞく)の復興現象とそれが意味するもの
改革開放政策以降の中国南部農村に続々と復興した宗族(そうぞく)組織。父系の親族が集落をつくって集居し、ともに祖先の墓や位牌を祭る。それは一見、高度経済成長を続ける現代中国には不釣り合いなアナクロニズムにも思えるが、近年の経済発展で得た富の社会的名声への変換、文革時代に破壊された人間関係の修復、あるいは中華文明の悠久の歴史と自己の祖系を同一視しようとする愛国主義的思潮など、多様に現代的な意味づけを施され再解釈された宗族の姿がそこには見いだされる。こうした現代中国の隠れた一面を、現地でのフィールドワークに基づく個別具体的な事例分析から明らかにする。
【主な研究テーマ】
● 親族関係と社会組織
● エスニシティー
● 華南地域研究

系譜を広げる(海南省タン州市)