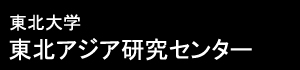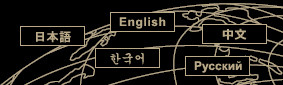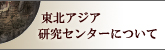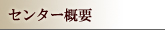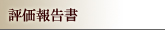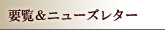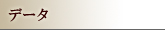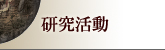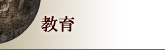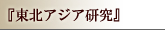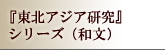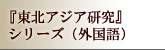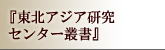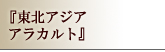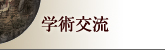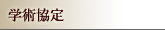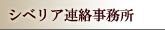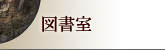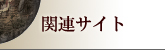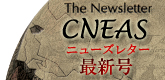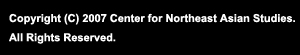日本列島の文化交渉史 ―経済と外交―
近年の歴史学では、グローバル・ヒストリーをはじめ、一国史的研究を克服し、複数の国・地域にまたがる考察が深められている。また、さまざまな専門家が事例を持ち寄り、学際的に分析を深めていこうとする傾向も増えてきた。私たちの共同研究では、このような研究の潮流に刺激を受けながら、東北アジア地域における日本列島の歴史的位置付けをおこないたい。今回の分析対象として取り上げたのは、経済と外交に関する諸問題である。この二つの問題から、「日本列島の文化交渉史」を明らかにしていく。
本研究の総論的位置には、中世から近世にかけての天草諸島(現熊本県)がある。天草は九州西部に浮かぶ島嶼地域で、古くから東シナ海を通じて諸外国との交流をおこなっている。その地理的特質から、経済活動や宗教の伝播、海外との接触について分析を試みたい。
経済に関しては、江戸時代の大名(藩)財政、関東地方の肥料(干鰯=魚肥)生産と流通、経済界をリードした三井越後屋の木綿取引などをテーマにしたい。藩財政、干鰯流通、三井の経営史といった内容はこれまで多くの研究が世に送り出されてきた。しかしながら、東北アジアにおける日本列島、もしくは日本列島の文化交渉の歴史という視角から考察を進めると、違った結論が浮かび上がる。
ここで述べる「外交」には、いわゆる国家外交というもの以外の民間の交流や対外政策に関わった人々の動きを含めている。明から清へと王朝が交替する中国の動きと日本の沿岸警備を考察する政策論をはじめ、近世の朝鮮通信使が日本の地域文化に与えた影響、明治時代の内国勧業博覧会が契機となった技術交流などに焦点をあてたい。また、19世紀末に日本からフランスへと渡る移民たちの動きを通じて、日本と諸外国の関係を双方向の視座でとらえる。
2013年度~2014年度
| 氏名 | 所属 |
| 荒武賢一朗 | 東北アジア研究センター |
| 小林 延人 | 日本学術振興会特別研究員PD |
| 下向井紀彦 | 公益財団法人三井文庫 |
| 鄭 英實 | 慶尚大学校慶南文化研究院 |
| 中山 圭 | 天草市役所観光文化部 |
| 宮坂 新 | 館山市立博物館 |
| ル・ルー ブレンダン | 帝京大学外国語学部 |
| 古川 祐貴 | 長崎県立対馬歴史民俗資料館 |
上廣歴史資料学研究部門ニューズレター「史の杜」などで紹介、次年度以降に公開講演会を開催、研究期間終了時に各論の原稿をまとめて論文集刊行を予定。