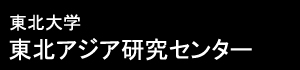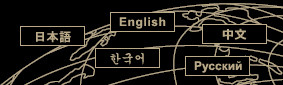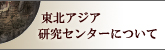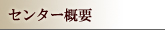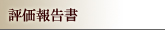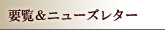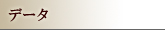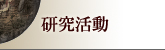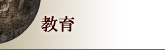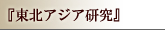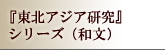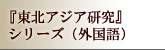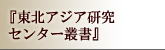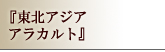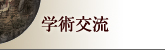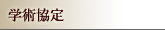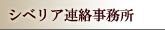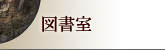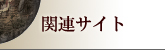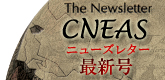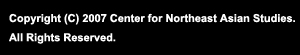江戸時代から現代に通じる東北の歴史
東北地方の歴史研究は、古代から近現代に至る長期的時間軸を視野に多くの成果が生み出されてきた。この共同研究では、とくに17世紀から20世紀前半のおよそ300年について、東北社会の歴史分析を主たる課題とする。目下、震災復興について日夜議論され、未来の地域社会の土台を構築されようとしている。そのなかで地域史研究はどのような貢献ができるのか。この問いかけは本研究の出発点となっている。大きな課題に直面しながらも、まずはここに参加する研究者それぞれが、かつて東北に住み暮らした人々の足跡を追いながら、現代社会にその実像を伝えたい。
江戸時代に相当する前半期では、「領主と民間社会」をキーワードにして、幕府領の支配構造、仙台藩における農地開発、盛岡藩内の民衆運動、米沢藩と経済システムなどを分析する。現代風にいえば、行政組織と地域社会の関係にも近似するが、当時の人々は「公」と「民」の関係をどのように切り結んでいたのかを地域資料に基づいて考察する。また、歴史上の重要な画期である明治維新期の秋田や宮城の事例をもとに、学問や経済構造のあり方を探求したい。秋田については稀代の国学者だった平田篤胤の影響を検討し、明治時代前期の宮城については三菱財閥の地域経済への参入過程を明らかにする。近現代における分析素材は、百貨店が登場することで劇的な変化を遂げる様相を「大衆社会」の誕生ととらえる。さらに、戦前の軍医とその妻が手掛けた社会事業と、戦後におけるハンセン病元患者の社会復帰など、当地の地域医療や社会事業の実像に迫る。
東北地方というひとつのエリアについて、地域に残った資料の積極的活用を進めていく。また、東北地方在住者とそれ以外の地域から参加する研究者が手を組むことで、資料情報の全国的な共有や、密接な議論をふまえての新しい成果を打ち出していきたい。
2013年度~2014年度
| 氏名 | 所属 |
| 荒武賢一朗 | 東北アジア研究センター |
| 加藤 諭 | 東北大学史料館 |
| 兼平 賢治 | 東北大学大学院文学研究科 |
| 佐藤和賀子 | 山形県立米沢女子短期大学 |
| 杉本 寛郎 | 所沢市生涯学習センター |
| 野本 禎司 | 德川記念財団 |
| 松岡 弘之 | 大阪市史料調査会 |
| 宮田 直樹 | 米沢市教育委員会 |
上廣歴史資料学研究部門ニューズレター「史の杜」などで紹介、次年度以降に公開講演会を開催、研究期間終了時に各論の原稿をまとめて論文集刊行を予定。