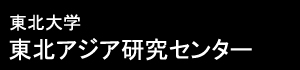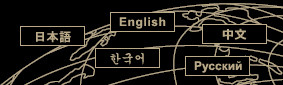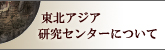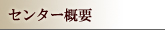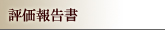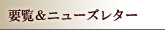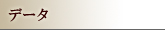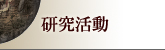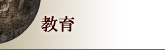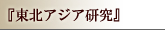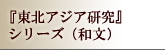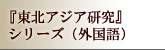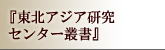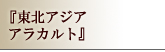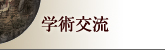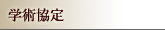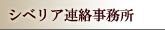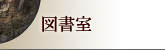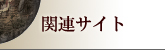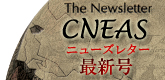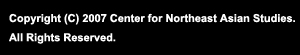PM2.5を中心とした東アジアにおける越境大気汚染に対処するための外交戦略に関する研究
中国や韓国からの越境大気汚染として飛来する、あるいは国内の汚染源から排出されるPM2.5問題に対する関心は非常に高い。それにもかかわらず、越境大気汚染への対処を可能にする外交戦略を提示するための研究は行われていないと言ってよい。事実、環境省が2013年12月に発表した「PM2.5に関する総合的な取組(政策パッケージ)」では外交戦略にはほとんど触れておらず、技術協力、地方自治体間の協力と、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)の活用が謳われているだけである。関連研究も基本的に大気科学による現象解明、そして工学的な排出量推計や対策技術の開発にとどまっている。その、EANETはその設立への議論が開始されてから20年以上が経つが、関連諸国の信頼を獲得するには至らず、その目標としていた東アジアにおける大気汚染対策の地域枠組みもその端緒を開くことすらままならない状況が続いている。
こうした認識に基づき、下記の研究を行う。
EANETの効果性評価
先述のとおり、PM2.5の対策としてEANETの活用が謳われているが、現在までの同組織の効果性を評価しない限り、本当にEANETがPM2.5問題の解決に貢献することができるのかは不明である。
越境大気汚染に係る国際環境協力制度間の相互連関の解明
越境大気汚染に係る国際環境協力制度はEANETだけでなく、他にも北東アジア環境協力プログラム(NEASPEC)、日中韓大気汚染物質長距離越境移動研究プロジェクト(LTP)などが存在する。PM2.5に対処するためには、こうした関連組織間の制度間相互連関を同定、分析し、現状の相乗効果と悪影響を明らかにすることで、これから相乗効果を高め、悪影響を排すことができるのかを提言することができるようになる。
越境大気汚染に対処するために設立された欧州や他組織における教訓の抽出
越境大気汚染への取り組みの先進事例として名高いのは、欧州越境大気汚染条約の経験である。その経験を東アジアに当てはめる場合、関連文脈が異なるという理由で棄却される場合が非常に多いが、アジアにおける関連文脈が教訓の有効性を低減させている事に関する精緻な分析は皆無である。このサブテーマでは当該教訓をレビューし、そうした教訓の適用条件を明らかにする。
2014年度~2016年度
| 氏名 | 所属 |
| 石井 敦 | 東北アジア研究センター |
| 岡本 哲明 | 東北アジア研究センター |
学会発表や論文掲載はもちろんのこと、センター長裁量経費で研究・提言内容に関する分かりやすいアニメーションを作成し、政策提言の内容を広く社会に普及させる。