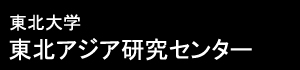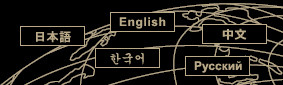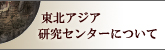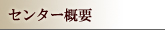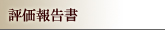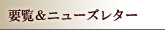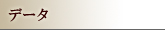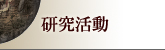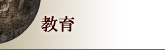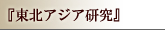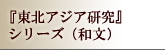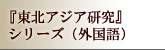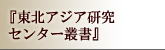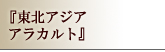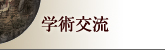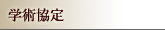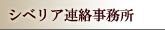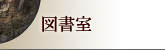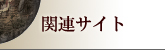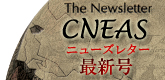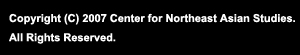遺跡にみる生物多様性研究
日本の生物相は有史以降の人間活動によって、大きく改変されてきたと考えられる。たとえば、耕作に伴う森林破壊や、狩猟、漁労による種や地域個体群の絶滅、人間が持ちこんだ外来種(帰化種)による遺伝子汚染、群集構造の改変など、人間活動は、さまざまな直接的、間接的なインパクトを生物相に与えてきたと考えられる。しかしその変化の詳細は、歴史的資料の乏しさから、よくわかっていない。
このような人間活動が顕在化するのは、日本では縄文期以降と考えられることから、縄文、弥生期の遺跡から出土する多彩な生物遺体は、漁労、採集を中心とした初期の人間活動が、生物相にどのようなインパクトを与えるかを知るための、優れたモデルとなる。またこの時代の生物試料は、その後の人間活動によって生物相が劇的に変化する直前の状態に関する情報を留めていると考えられ、本来の日本の生物相の実態を知るために活用できる。
そこで本研究では、宮城県の縄文遺跡、特に貝塚を中心に、産出する生物遺体の遺伝子解析と安定同位体分析を主として、この時代の動植物の遺伝的変異や生態系構造を推定する。宮城県は日本有数の貝塚の分布地であり、特に還元的環境に埋積した保存状態の良好な貝塚が多いことで知られている。脊椎動物の骨や植物遺体、巻貝の殻頂内部や二枚貝の蝶番は、遺伝子が残存している可能性が高く、その変異を異なる時代の遺跡試料間で比較することにより、集団の遺伝的構造の変化、異なる系統の集団の移住などを推定する。さらに安定同位体比の分析により、食物網の変化を解明し、人間活動が及ぼす生態系への影響を推定する。さらに現生のものとの比較により、その後の大きな環境改変が日本の生物相、特に遺伝的多様性と生態系構造をどのように改変したのかを明らかにする。
2015年度~2017年度
| 氏名 | 所属 |
| 千葉 聡 | 東北アジア研究センター |
| 阿子島 香 | 東北大学大学院文学研究科 |