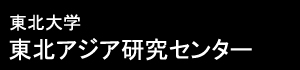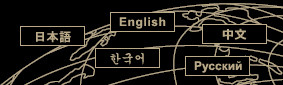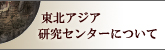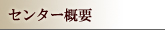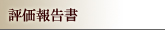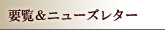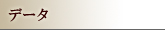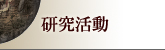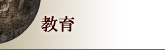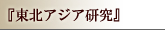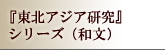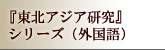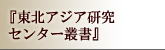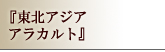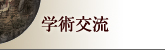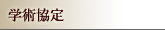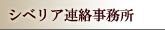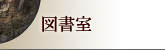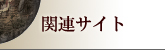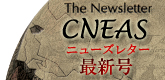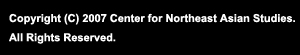モンゴル語、日本語、中国語の文法カテゴリーの対照研究
ある言語の文法は、他の言語の文法の枠組みで書かれることが多い。モンゴル語の文法も、研究者によって、ある場合にはロシア語文法の枠組みで、またある場合には中国語文法の影響を強く受けている。それは、品詞分類から個々の文法的カテゴリーに至るまで、あらかじめ存在する枠組みによって事実を分類し、説明するやり方である。
本研究では、名詞類の格、数、所属、動詞類の時制、人称、(命令、願望、陳述等の)式、法、態、さらに形動詞や副動詞と呼ばれている活用形式について、それら機能的観点から再検討を行い、モンゴル語に内在する特徴を明らかにしようとするものである。
研究方法としては、モンゴル国のロブサンワンダンの文法理論を手掛かりに、モンゴル語の文法的カテゴリーを個々にとりあげ、それらの形態と機能を検討する。研究に際しては、日本語と中国語を対照することによって、それらの文法的カテゴリーの機能の比較を行い、共通点と相違点を示すことによってモンゴル語特徴を明らかにする。 個々の文法的カテゴリーを取り上げる際には、過去にロシア語、中国語、英語、モンゴル語で書かれた主要な文法書による扱いを調査して、それらがモンゴル語文法の枠組み形成に与えた影響を明らかにする。
2015年度~2016年度
| 氏名 | 所属 |
| 栗林 均 | 東北アジア研究センター |
| 崔健(サイケン) | 北京語言大学 |
| セチンゴア | 東北アジア研究センター |