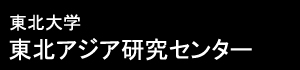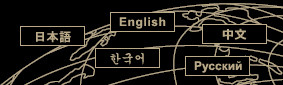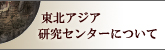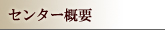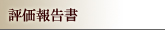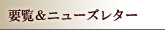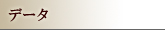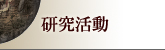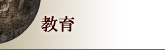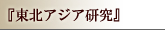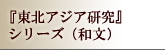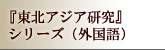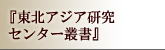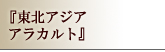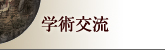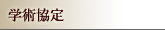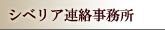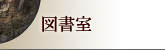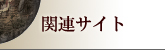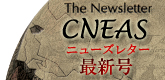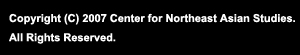東北アジア辺境地域多民族共生コミュニティ形成の論理に関する研究
清代から近代にかけての東北アジア辺境地域では、活発な人と物の移動が見られた。この移動は、辺境部にマルチ・エスニックな社会を出現させた。辺境社会に関する従来の研究においては、民族間の相克・対立や、文化的同化やネーション・ステートの形成といった問題に関心が集まってきた。しかし辺境部に形成された複合的な社会においては、決して単に対立構造のみが形成されたわけではなく、現実的な問題を解決する中で多民族の共生構造も生み出された。統治を担う国家の政策も、このような共生構造に規定されながら定立されたのであって、一方的な対立構造のみで捉えることはできない。本研究では、清代において長城線・劉条辺牆線を挟んで区分されていた中国本土とモンゴル地域、国境を挟んだロシアと中国の間の人と物の移動が生み出す民族的共生構造の解明を目的とする。前者に関しては、漢人の移住によって定着化したモンゴル人と漢人移住者の社会関係とこれに対する国家統治の在り方が問題となり、後者においては主に清末から民国期・満洲国期におけるロシア人と中国の関係の様態が問題となる。この研究を通じて、共生構造の複合的性格を、当事者たる一方の民族・国家の立場からではなく、双方向的・相補的な観点から解明することを目指す。また本研究を通じて、歴史上の問題としてばかりでなく、現在における東北アジアの多民族的構造の理解にも示唆を得ることが期待される。
2015年度~2018年度
| 氏名 | 所属 |
| 岡 洋樹 | 東北アジア研究センター |
| 堀江 典生 | 富山大学極東地域研究センター |
| 藤原 克美 | 大阪大学大学院言語文化研究科 |
| サヴェリエフ・イゴリ | 名古屋大学大学院国際開発研究科 |
| 広川 佐保 | 新潟大学人文学部 |
| 橘 誠 | 下関市立大学 |