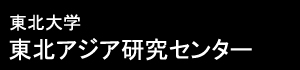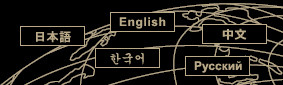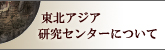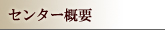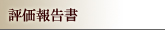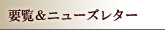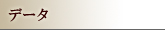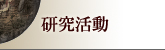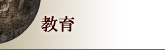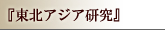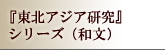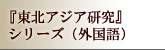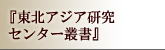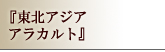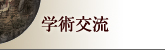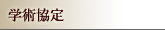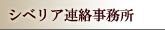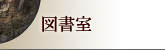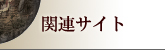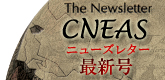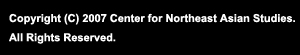東北アジアに分布する広域変成岩・変形岩の連続性検証手法の総合研究
【目的】
東北アジア地域の鉱物資源の分布は地質、すなわち過去の造山運動の様式と密接な関係がある。特に、造山帯中の変成岩・変形岩(オフィオライトの構成岩類を含む)は、広域的地域地質の発達史において、造山運動が関与した鉱物資源の成因の因果関係を紐解くための鍵になる。本研究は国内外の研究者を招聘して、東北アジアの変成岩・変形岩の連続性検証手法に関してシンポジウム形式で議論する。
【方法】
造山帯は帯状に形成・発達する。一般に、古い時代の造山帯において、地表で特定の岩石の連続が追跡されない場合、間接的な証拠を総合して初生的な地質の連続性を想定することになる。例えば、中生代トリアス紀中頃の北中国地塊と南中国地塊の衝突・縫合境界は超高圧変成岩の分布で追跡可能である。しかし、超高圧の証拠を欠く地域では検証が必要となる。本研究は広義の変成岩・変形岩の研究に携わっている研究者(学生を含む)を国内外から約60名を集め、参加者の研究成果をシンポジウム形式で議論することで、連続性検証手法の総合理解をめざす。
【期待される成果】
平成28年度、東北アジア研究センターの新規のユニットとして、『東北アジアにおける地質連続性と「石」文化共通性に関する学際研究ユニット』(代表:辻森)が発足した。このユニットは、いわゆる翡翠など、人類史の「石」文化に着目し、自然科学と人文科学分野の文理連携によるクロスオーバー型啓蒙活動のモデルの新提案を目指すものである。本研究は、同ユニット研究に関して特に変成岩岩石学に関係した専門知識を供給し、より総合的な視点を提供する。
【共同研究の理由】
研究組織のうち本学環境科学研究科の土屋教授らのグループ及び、九州大学の小山内教授、地球年代学ネットワークの板谷理事は、本研究に関連して優れた実績があり、国内外に幅広い研究者ネットワークをもつ。彼らと共同して、シンポジウムを開催することで、上述のユニット研究も含めた相補的な新展開が期待される。
2016年度~2016年度
| 氏名 | 所属 |
| 辻󠄀森 樹 | 東北アジア研究センター |
| 平野 直人 | 東北アジア研究センター |
| 土屋 範芳 | 東北大学環境科学研究科 |
| 岡本 敦 | 東北大学環境科学研究科 |
| 小山内 康人 | 九州大学比較社会文化研究院 |
| 板谷 徹丸 | 地球年代学ネットワーク(NPO法人) |