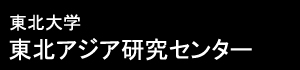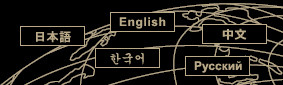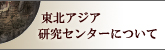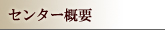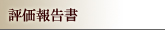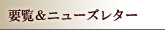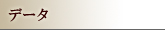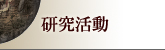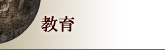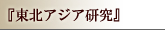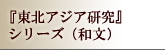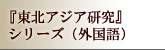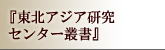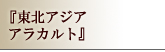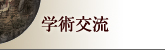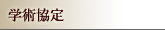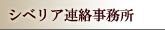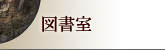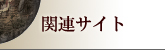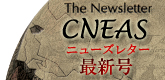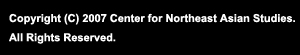石材利用戦略と文化交流の解明による東北アジア「石」文化形成史の復元
人間活動が石器製作伝統、すなわち「石」文化によって語られる旧石器時代においても、東北アジアは異なるルートを経由し拡散してきた、それぞれ固有の「石」文化を持つ人類集団が合流する、ダイナミックな文化の変容と交流の舞台であった。一例として、シベリアから北海道を経由する「北ルート」の「石」文化と、朝鮮半島から九州に到達する「南ルート」の「石」文化とが衝突し、ついには融合を果たした地が日本の東北地方だと考えられる。このような東北アジア「石」文化の総合理解に到るには、集団固有の「石」文化の形成過程と、集団間の交流の双方を解明することが不可欠である。そして前提として「石」文化の在り様は利用可能な石材に大きく制限されるため、地質学的「石材環境」を理解しなければならない。そこで本研究では、石器および石材環境の分析を通じて、(1) 人類がその拡散過程でいかに各地の地質学的環境に適応したかという「石材利用戦略」と、(2) 先史時代の文化交流という二つの側面から「石」文化の形成プロセスの理解を目指す。
本研究では、上記東北地方の地理的利点を活かし、後期旧石器時代(3万年~2万年前)に属する石器の分析を通じて石材の利用戦略と文化交流の二側面から東北アジアの「石」文化形成史を解明する。石器は形態・製作技術・石材という三要素からなる。地質学データから東北アジアの石材環境を復元し、南北の各ルートで石材環境の変化が形態と製作技術に与えた影響と、どのような石材を利用しているかという石材利用の変化を分析する。さらに、石器の形態と製作技術を属性抽出もしくは定量化した後、日本列島での文化交流に際して交換された属性と同化の速度を明らかにする。そのことによって、東北アジアの多様な「石」文化の形成過程の解明に寄与できると同時に、長期的な文化交流のプロセスを人間行動のレベルから基礎付けることができると期待される。
2016年度~2016年度
| 氏名 | 所属 |
| 田村 光平 | 東北大学・学際科学フロンティア研究所 |
| 熊谷 亮介 | 東北大学文学研究科・博士課程後期 |
| 洪 惠媛 | 東北大学文学研究科・博士課程後期 |
| 阿子島 香 | 東北大学文学研究科 |
| 辻󠄀森 樹 | 東北大学・東北アジア研究センター |