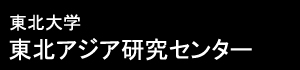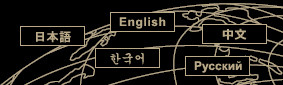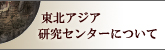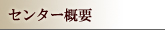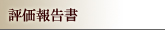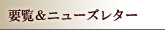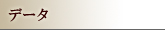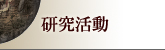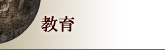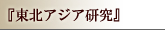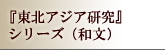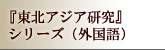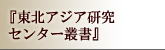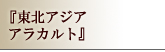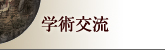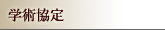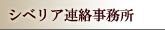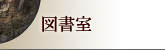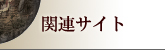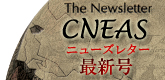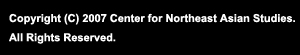宝石資源を持つ自然遺産の持続可能な保全のための学際的研究
昨年(2016年)、地球惑星科学系の日本学術会議協力学術研究団体の複数がそれぞれ独自の事業として「県の石」(日本地質学会)と「国石」(日本鉱物科学会)を相次いで認定した。世界に目を向けても、ユネスコが認定する「世界ジオパーク」など、価値の高い「石」に係わる自然と文化は自然遺産として保護の対象とされ、地域理解のための重要な素材となっている。わが国においては、国(文部科学省)及び各都道府県が文化財に指定する「地質・鉱物天然記念物」が存在する。学術上貴重で、地域の自然を代表する「石」に関して、その多角的な価値の啓発が計られてきた。最近では、文化庁が 「日本遺産(Japan Heritage)」に「石」に係わる地域史を認定した例もある。これらは我々人類が旧石器時代以降、テクノロジーとして「石」を利用し、装飾品として「石」文化を形成してきた延長にある。一般に、自然遺産は野外での見学が可能であって、法律による保護などによって持続可能であることが重要視される(ここでの持続は、人類の歴史という未来も含む曖昧な時間スケールで、地質学的な長期的な時間スケールに比べれば極めて短期である)。しかし、自然遺産のなかでもとりわけ、希少性の高い宝石資源を持つ対象の保護には盗掘をはじめとする固有の問題が伴う。その一方で、持続性を十分に考えなかった保護や過度な保護による弊害もある。十分な学術的研究と地域理解が相補的に関係してはじめて持続可能な保全が実現する。
本研究では世界の「翡翠(ひすい輝石岩)」産地の持続可能な保全に関して、1)既に自然遺産化として厳重に保護されてきた産地と、2)全く保護されずにきた産地に関して、現状とそれぞれの産地の現状と問題点を調査し、両者を比較する。そして、自然遺産及びそれに相当する価値の天然物(地質・鉱物)の持続可能な保全に関して、地域との共存のありかたの提言を目指す。
本研究は「東北アジアにおける地質連続性と「石」文化共通性に関する学際研究ユニット(代表:辻森)」に関連し、派生するものである。同ユニットが先史時代に着目しているのに対し、本研究では現代社会から要求される「自然遺産の持続可能な保全」についての地域研究を行う。遺産化、文化財化、シンボリック化など、現代社会の「石」文化から新しい地域理解の基軸を見出す。
2017年度~2017年度
| 氏名 | 所属 |
| 鹿山 雅裕 | 東北大学学際科学フロンティア研究所 |
| 辻󠄀森 樹 | 東北アジア研究センター |
| 高橋 菜緒子 | 東北大学大学院理学研究科 |
| 宮下 敦 | 成蹊大学理工学部 |
| 谷 健一郎 | 国立科学博物館 |