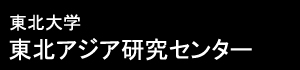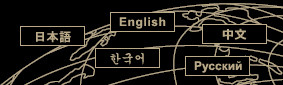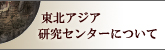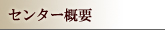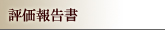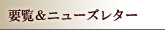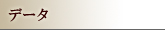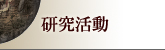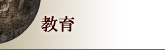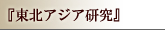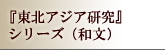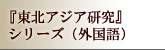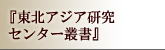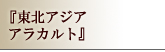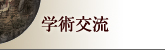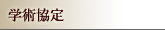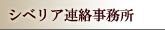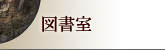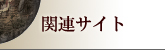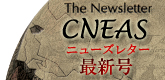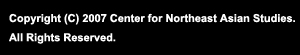複眼的方法論からみる中国における権威主義体制の強靭性
1970年代後半に東欧を中心に民主化が起こり、その後東アジア諸国へと拡大した。また、2010年にはチュニジアでジャスミン革命が起こり、それを契機として大規模な民主化運動が中東諸国に波及した。大規模な民主化の波が発生するたびに、中国の権威主義体制の脆弱性及び民主化の可能性は注目を集めた。しかしながら、そういったある種の「期待」を裏切り、中国の権威主義体制は依然として持続している。このような歴史的背景を鑑み、現代中国政治研究の主要な関心は、民主化論から権威主義体制の構造の解明へと移りつつある。また、権威主義体制研究の中でも中国という事例は、常に新しい知見を研究者に与え続けている。
中国共産党がどのように権威主義体制を維持してきたのか、という問題に対し、元来、歴史学に縁のある日本の現代中国政治研究は、その手法を用い、質的(qualitative)で叙述型の研究を進めてきた。翻って、欧米の学術空間では、量的(quantitative)な研究が中心である。このような両者の研究姿勢は、利点と不利点がある。前者は、中国共産党の一党体制の歴史的な変化を理解する一助になるが、権威主義体制の持続を構造的に解明することには不向きである。後者は、中国で発生する実証的な事例と権威主義体制の持続の因果関係を明らかにできるが、時間軸を捉えきれていない。
本研究は、これまでの研究の課題を踏まえ、現代中国政治研究という地域研究と権威主義体制研究という比較政治研究の融合を可能にするべく、新たな方法論を探求することを目的とする。具体的な研究活動として、第一に、質的研究に従事してきた若手研究者とともに、量的研究の手法を獲得することを目指す。第二に、研究代表者及び分担者それぞれが異なった学問領域を専門とすることから、各々の質的調査の方法論を教授し、歴史学と政治学、政治学と社会学、社会学と歴史学といった学問横断型の質的方法論の追求を行う。第三に、研究分担者は中国以外の地域(主に日本)を専門とすることから、方法論を基盤とした比較研究の可能性について議論する。
2017年度~2017年度
| 氏名 | 所属 |
| 内藤 寛子 | 東北アジア研究センター |
| 菊池 映輝 | 文教大学 |
| 松谷 昇蔵 | 早稲田大学文学研究科 |
| 三谷 宗一郎 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 |