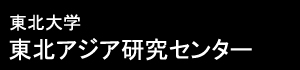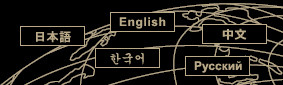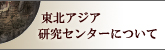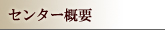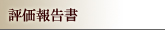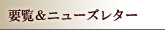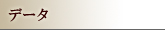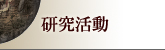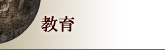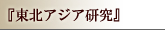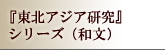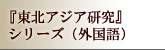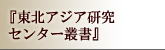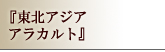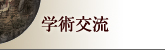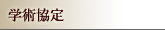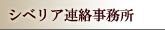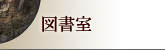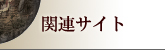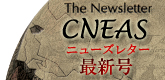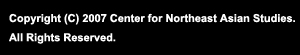地質遺産の持続可能な保全のための学際研究:広域変成地域の伝承的信仰
本研究は地質遺産の保全と継承に関しての学際研究を理系分野の研究者が中心となり、文系分野の手法を取り入れながら、新しい学際研究の可能性を実践的に模索する。近年、地学的(地質学的)に重要で、学術性の高い場所を自然遺産として整備し、専門的な研究だけでなく、地域の自然史の理解、それを通した科学教育、さらには観光資源の開発など多角的な事業が国内外で展開されている(例えば、ユネスコ世界ジオパークなど)。国内でも体制整備の他、さまざまな規模の組織で自然遺産としての価値の評価や推薦、認定などが行われている。それら一連のムーブメントによって、「自然・文化遺産の保全と継承」は社会からの期待が寄せられている学際研究領域となった。本研究は「東北アジアにおける地質連続性と「石」文化共通性に関する学際研究ユニット(代表:辻森)」に関連し、結晶片岩(広域変成岩の一種。地下深部で剪断応力を受けながら再結晶することで片理と呼ばれる面状の構造が発達する。「三波石(群馬)」、「秩父青石」(埼玉)、「伊予青石」(愛媛)など庭石の材料としても日本文化に根付いている)が分布する地域の伝承的信仰に着目する。日本列島のような海洋プレートが沈み込むプレート収束境界には、過去のプレート沈み込みで形成した結晶片岩が分布する。結晶片岩が分布する地域は比較的急峻な山地が多く、景勝地になるような渓谷の他、地域的な言い伝えや伝承的信仰の対象になるような露頭や伝承的信仰に関係した習慣・風習が残っていることが多い。本研究では結晶片岩分布地域において、オーラルヒストリー・聞き取り手法を導入しアーカイブを作成する。民俗学的なアプローチを複数の結晶片岩分布地域で行い、地域のなかでどのように民俗信仰の露頭が保全されてきたのか、その共通性を探る。そして現代社会が要求する天然オブジェクトの遺産化の本質を評価する。
2018年度~2018年度
| 氏名 | 所属 |
| 辻󠄀森 樹 | 東北アジア研究センター |
| 宮下 敦 | 成蹊大学理工学部 |
| 鹿山 雅裕 | 東北大学学際科学フロンティア研究所 |
| 進士優朱輝 | 東北大学理学研究科 |
| 青木 一勝 | 岡山理科大学基礎理学部 |
| 板谷 徹丸 | NPO地球年代学ネットワーク |