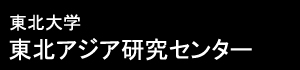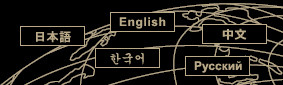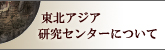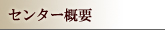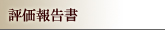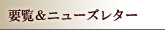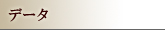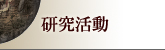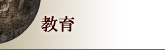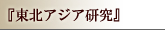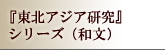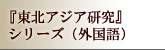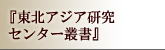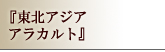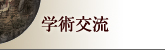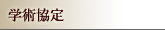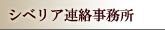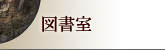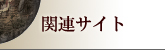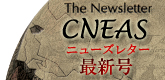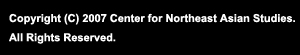規範と模範:東北アジア地域における近代化と社会共生
前近代の東北アジアにおいて社会共生の規範(ルール)と模範(モデル)を形成してきたのは、儒教・仏教・道教であった。家族親族に関する儀礼や慣習は主として儒教に基づき、年中行事や地縁的な儀礼は仏教や道教に根ざしていたが、アジア諸国における近代化は、伝統的な規範と模範に基づく社会を大きく変容させた。規範と模範という視点から東北アジアの近代を眺めると、近代化という合理的な模範と模範の導入によって、伝統的な規範と模範が解体し、新しい社会共生の規範と模範が生成される過程が見えてくる。例えば、明治日本の近代的学校制度や金融制度、交通制度などは西洋を模範したもので、大学や銀行、官庁、駅舎などの赤レンガの建物そのものが西洋近代を模範している。近代化の過程で新しい規範を模索する必要に迫られた新しい世代と、前近代の規範と模範に従う古い世代との間で葛藤が起こったことは、多くの先行研究が指摘するところである。
明治日本では模範先行の近代化が図られたのに対して、中国などの社会主義国では社会主義という規範が前景化した近代化が図られた。中国は、儒教的規範を破壊すると同時に、工場の国営化や農業の集団化を通して資本主義国とは別の規範を創出し、その規範が模範的労働者や模範的兵士という社会主義的模範の形を生み出した。古い規範を破壊する行為は、文化大革命においてピークに達した。社会主義的模範の創出や伝統的規範の破壊行為はあったものの、結局のところ、それらは広い眼で見れば、近代化の道から離れたものではなかった(小長谷有紀他編『中国における社会主義的近代化:宗教・消費・エスニシティ』勉誠出版、2010年)。これらの点を踏まえて、本研究は東北アジア地域における規範と模範の個別の事例を比較検討し、東北アジアにおける近代とは何だったのかを何かを改めて考察する。この点において本研究は、「中国・朝鮮半島・モンゴル・ロシアを総合的に理解する」ことを目指す貴センターと目的意識を共有する。貴センターが目指すところと同様に、本研究もグローバル化の中で規範と模範が揺らぐ現代の東北アジアの社会共生に必要な視座を提供することを目指す。
2018年度~2018年度
| 氏名 | 所属 |
| 高山 陽子 | 亜細亜大学国際関係学部 |
| 瀬川 昌久 | 東北アジア研究センター |
| 李善姫 | 東北アジア研究センター |
| 山口(加藤)睦 | 山口大学人文学 |
| 稲澤 努 | 尚絅学院大学総合人間科学部 |
| 孫潔 | 佛教大学 |
| 中村 知子 | 茨城キリスト教大学・日本大学 |
| 兼城 糸絵 | 鹿児島大学法文学部 |