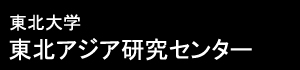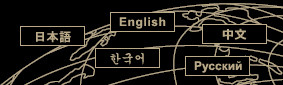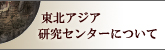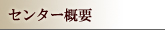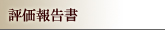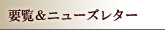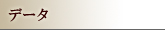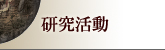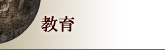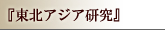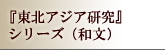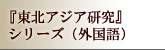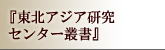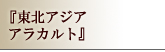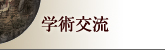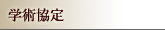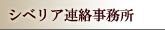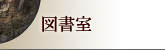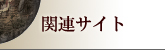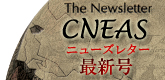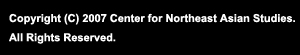新型感染症の発生がもたらす社会的格差の拡大:マイノリティグループに着目して
新型コロナウイルスの発生は、人々の生活に多大な影響を与えている。この中、脆弱性の高いマイノリティグループや社会的弱者が受けた打撃がより大きいと考えられる。本共同研究は、①在日中国人、②居住弱者、③ひとり親世帯、④多重災害被害者に着目し、新型コロナウイルスの感染拡大が彼らの行動·生活・仕事等に与える影響を調査し、ウィズコロナ時代における地域共生社会に向けた包括的支援の在り方を探る。
新型コロナウイルスの感染は、まず震源地である中国武漢で拡大してから、世界各地で中国人差別事件が起きている。このような心理的な負担のほか、母語情報不足、収入減少や母国との移動制限など、パンデミックにおいて、在日中国人住民はローカル住民と比較してより多くの課題に直面している。災害時における彼らの行動・生活状況を理解することは、多文化共生と災害対応の両方の観点において重要である。
次に、日本での感染拡大後、全国各地で外出自粛が要請された。外出自粛期間中、居住弱者(最低居住面積水準未満の世帯)が、比較的不利な状況にある居住空間にいる時間が大幅に増加したため、住宅・居住環境がその健康に与える影響はより大きくなると考えられる。ウイズコロナ社会における居住環境に起因する健康格差の解消に対して、彼らの自粛期間中の行動(外出や健康行動の実施など)と、主観的健康感の変化およびその中における居住環境の影響の解明は重要である。また、緊急事態宣言中に多くの保育所が休園や利用自粛の状況になったことは、子育て世帯に大きな影響を与えた。在宅勤務が可能であっても、家庭で仕事をしながら子育てをすることの困難さや非効率さは避けることができない。特にひとり親世帯においては、家事や子育てにおいても配偶者の助けが受けられない。保育所の休園や利用自粛によるひとり親世帯の子育て状況や労働環境の変化を理解することは、今後の社会で必要とされる保育サービスの解明において不可欠である。さらに、東日本大震災、昨年の台風19号、今年7月の九州豪雨などの自然災害被災者は、コロナ禍との複合リスク・多重被害を受けている。ウィズコロナ時代における多重被害からの生活再建は、自然災害の多い日本における新たな課題である。
2020年度~2020年度
| 氏名 | 所属 |
| 滕 媛媛 | 東北アジア研究センター |
| 中山 愛子 | 東北大学経済学研究科 |
| 高千穂 安長 | 東北大学経済学研究科 |
| 稲葉 雅子 | 東北大学経済学研究科 |
| 増田 聡 | 東北大学経済学研究科 |
| 中村 哲也 | 共栄大学国際経営学部 |
| 竹本 圭介 | 藍野大学医療保健学部 |