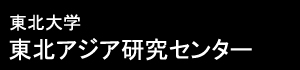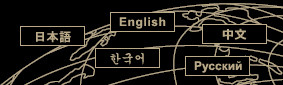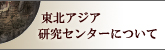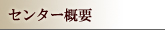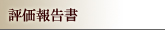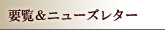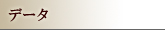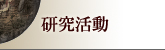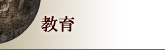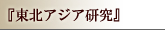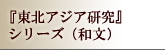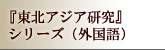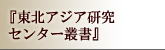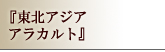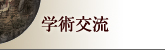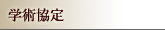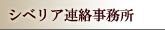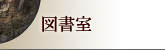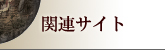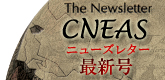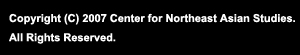18世紀および19世紀のサハリン・千島アイヌの歴史民族学的研究
北海道、サハリン(樺太)及び千島列島に居住していた先住民族であるアイヌは、居住地域ごとに歴史的に異なる発展過程をたどり、それぞれ特徴ある文化様式を作り出した。近世には北海道アイヌと周辺地域(サハリン島、千島)との交易が行われ、サハリンを中継地として行われた山丹交易はアムール下流地域や沿海州まで広がり、また千島列島に沿った千島交易はカムチャツカ半島まで及んだ。サハリンアイヌと千島アイヌを仲介者とした諸民族間の交易が行われ、交易品は松前藩を窓口として本州へと流通した。
18世紀には、ロシアによる千島南下開始、東蝦夷地(道東)で起きたアイヌ蜂起、ロシア使節ラクスマンの根室来航などを契機に北方地域に対する幕府の意識や政策が転換し、18世紀末からの蝦夷地(北海道)の直轄化へとつながった。このような政治動向の変化は北海道と周辺地域との交易にも影響を及ぼした。
1855年に日露和親条約が締結され、両国間の国境が千島のエトロフ島とウルップ島の間に決定された。続いて1875年の千島樺太交換条約によって、千島列島は日本領、樺太全島はロシア領となり、それぞれの地域の先住民は日露いずれに属するかの選択に迫られ、樺太アイヌの対雁(石狩)、また千島アイヌの色丹島への移動をもたらした。
本研究の目的は、上記のような歴史政治的背景を持つ日本の北辺(北海道、千島、サハリン)と周辺地域(沿海州、カムチャツカ半島)を一つの領域として設定し、18世紀と19世紀の時期を対象に、日本、ロシア、アイヌの相互接触および相互関係の実態を明らかにすることにある。本研究では、特に日本とロシアの狭間に置かれたサハリンアイヌと千島アイヌの歴史的発展に焦点を当て、いまだ十分な検討がなされていないその実態を究明したい。そのために、本プロジェクトに加わる研究者の多様な視点(歴史、民族、美術)からの考察は極めて有用であり、アイヌの歴史の解明に役立つと思われる。
2020年度~2020年度
| 氏名 | 所属 |
| 遠藤 スサンネ | 東北大学高度教養教育・学生支援機構/東北アジア研究センター兼務教員 |
| 高倉 浩樹 | 東北アジア研究センター |
| Sofya Lim | North-Eastern Federal University, Russia |
| 松本 あづさ | 藤女子大学 |
| 井上 瑠菜 | 東北アジア研究センター |
| 菊池 勇夫 | 宮城学院女子大学 |