

 |
| 自然・環境 |
| 歴史・文化 |
| 言語 |
| 社会貢献 |
| もっと東北アジアを知る |
| ニューズレター「うしとら」 |
| 催し物 |
| 懇話会について |
| 入会案内 |
| お問い合わせ |
| TOPページへ戻る |
| サイトマップ |
| 関連リンク |
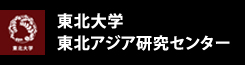

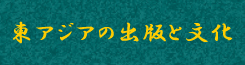
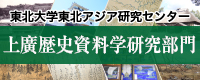

|
事務局 〒980-8576 仙台市青葉区川内41番地 東北大学 東北アジア研究センター内 東北アジア学術交流懇話会 |
TOP < 東北アジアにふれる < 社会・経済
![]()
![]()
シベリアのサハ共和国、極寒の地で知られるヤクーツクから、50キロほど離れた農村地域を対象に、そこに暮らすサハの人びとの環境変化の認識について、アンケート調査を実施しています。
私がこの地を初めて訪れた冬の2月は、凍てつく白銀世界で、日中でもマイナス30度ほど。各世帯を歩いて訪問し、シャツでもすごせる温かい家のなかにいれてもらい、アンケートに答えてもらいます。お礼をいって防寒をして家からでると、再び凍てつく寒さを体感することになるのですが、家のまえにしばしばみられる、かわいらしい雪でできた犬の造形が、心をあたためてくれます。
同様の調査を夏にもおこなったのですが、冬のシベリアの季節とは景観が異なります。冬の白銀世界とはうってかわり、家のベランダにならべられた植木鉢から花も綺麗に咲いています。8月のシベリアは気温も20度前後と大変過ごしやすく、家回りをゆっくりと見て回ることもできます。私がまず目についたのは、家のまえにおかれている、かわいらいしい木の鹿の小さな造形物が、心をあたためてくれます。ちょっと目をそらしてみると、家のまわりには、家をあたためるための薪が積まれています。
夏と冬の対照的な季節の調査を通じて、サハの人びとは、心身ともにあたたかく過ごす些細な工夫なようなものを家まわりからみてとることができました。
東北大学 東北アジア研究センター 学術研究員 田中 利和 |
|
|
|
|
![]()
ロシアは多民族国家でもあり、多宗教国家でもあります。近年ロシアでは、その歴史的な多宗教性を利用した国民統合のあり方が政府によって模索されており、国家と宗教の関係に対する注目が高まっています。ロシアというとロシア正教のことを思い浮かべる方も多いと思いますが、1997年に制定された「良心の自由と宗教団体に関する」ロシア連邦法(No125-F3)では、「キリスト教、イスラーム、仏教、ユダヤ教」がロシアの「伝統宗教」として明記されています。ここで言うところの「仏教」はチベット仏教です。特に仏教信仰の盛んな地域としては、シベリアのブリヤート共和国やトゥヴァ共和国、ヴォルガ・ドン地域のカルムィク共和国があります。筆者はこれまで、特にカルムィク共和国の教団に注目してきました。ソ連時代に寺院も教団も完全に破壊されたカルムィク共和国では、すべてを一から始めなくてなりませんでした。教団のトップをアメリカから招き、ダライ・ラマから派遣されたチベット人高僧が彼を補佐するとともに僧侶と衆生の教育に尽力しました。現在、インドのダラムサラなどに留学していた若いカルムィク人僧侶たちが長年の修行を終え、続々故郷に戻り始めました。このように、カルムィク共和国の仏教復興運動は新たな段階に進みつつあり、今後も目が離せません。
元・日本学術振興会特別研究員PD(東北大学東北アジア研究センター) 井上 岳彦 |
|
|
|
|
ウラーンバートルの文書館調査のかたわら、友人とともに地方に出かけ、ブルガン県にある遊牧民のお宅に滞在しました。ウラーンバートルの町を出ると、すぐそこは遊牧民の世界です。彼等は、馬・牛・羊・山羊・駱駝などの家畜を放牧し、乳製品・肉・毛・皮などを用います。こどもたちもとても見事に馬を乗りこなします。彼等の家はゲルと言い、木製の壁・天井・屋根・扉を家畜の毛で作ったロープで結びつけて建てます。建てるのに40分くらい、解体に30分くらいかかります。夏の間彼等は、ゲルを中心に家畜の群れを放牧し、家畜に草をいっぱい食べさせながら移動を繰り返します。ですからとても忙しいのです。次々に出入りする近所の遊牧民達の話に耳をすますと、どこの牧地が空いているか、誰がいつごろどこに移動するのかといった情報を交換しているのがわかります。 モンゴルの遊牧民はとても客好きです。私が訪れた時も、写真のように、山羊を屠殺してふるまってくれました。草原で食べる肉料理はとても美味です。珍しい日本人の客が来たと聞いて、近所の住民が集まってきました。お酒を飲みながら、夜中過ぎまで歌を唱います。
東北大学 東北アジア研究センター教授(東洋史・モンゴル史) 岡 洋樹 |
|
|
![]()
シベリアにはロシア人などのスラブ系の住民以外に、40にも及ぶアジア系の先住民が歴史的に暮らしてきました。彼らは言語的にはフィン語やハンガリー語と類似するものから、トルコ語やモンゴル語、ツングース語系、さらに歴史的には彼らより以前からシベリアに暮らしてきた古アジア系の言語集団まで多様です。このような言語的多様性にも関わらず、トナカイを資源として利用する伝統的な経済が共通して形成されてきました。それは大型有蹄類としてツンドラとタイガという生態系に圧倒的に優勢な地位を占めるこの動物が、衣食住に利用できるだけでなく、家畜として騎乗と橇牽引として利用しやすい習性をもってきたからです。野生トナカイを狩猟し、家畜トナカイを飼育する生業はシベリアの人類史を理解する上で重要であるだけでなく、ロシア=シベリアの社会主義化=近代化、さらに近年は天然資源の開発、北極圏の気候変動という観点からの学際的な研究においても着目されています。また、その人・家畜関係は、モンゴルや中央アジアにおける遊牧の歴史を考える上でも重要な位置づけを持っています。
東北大学 東北アジア研究センター教授(社会人類学・シベリア民族誌学) 高倉 浩樹 |
|
|
|
|
|
©2013 東北アジア研究センター 東北アジア学術交流懇話会 All Rights Reserved. |













